総本部夏合宿最終日の早朝稽古は、改定IKOルールに則った上段蹴りのクリーンヒットからの残心、捌きや捌きからの返し、押し技の稽古でした。



朝食後、部屋の片付けをします!
無事に道場に到着し、合宿の全日程が終了しました。
極真会館総本部道場 澤村勇太
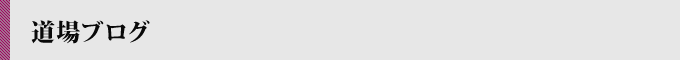
朝は5時に起きます!
そして、最初の稽古はマラソン大会です!

日本代表の上田選手も参加し、4位に入賞しました。
10kmは大変な子どもたちにとって大変な距離ですが、諦めずに最後まで頑張りました!
完走できなかった子は鍛え直して、来年チャレンジしよう!
岡初段は安定の1位。通算10連覇だそうです!すごい!
朝食を取り、本日2回目の稽古です。
野外稽古では基本→移動→約束組手→班別稽古→リレー大会を行いました。

気温や日差しが強く、厳しい環境でしたが、それこそ極真カラテ!いかなる状況にも対応できるように鍛錬します!
午後の稽古は赤石先生の型の稽古を行い、その後は綱引き大会を行いました!
子どもたちのテンションは最高潮に!笑
皆で前で芸を発表するのは恥ずかしいものですが、それも稽古!
今回はレベルが高く接戦でしたが、我ら総本部少年部が属する少年1班が優勝!
皆、堂々と、そして面白くできました!
極真会館総本部道場 澤村勇太
空手は柔軟体操もよくやりますので、足が高く上がるようになります!
極真会館総本部道場 澤村勇太
帯のテスト(昇級審査会)で合格した子に新しい帯が届きました。
漠然と頑張るよりも、黒帯を目指して頑張る方が、子どもたちにとってわかりやすく、稽古の集中力が変わってきます。
新しい帯が来て、嬉しそうです^^
極真会館総本部道場 澤村勇太
総本部道場では黙想を長めに取り入れています。
小さい子は4歳からいます。
最初は動いしてしまい、なかなか黙想ができませんが稽古を重ねていくうちにできるようになっていきます。
黙想のポイントは、姿勢を正しく、動かない、何も考えない。
この稽古は継続していくと、姿勢が整っていき、集中力が付いてきます!
極真会館総本部道場 澤村勇太
選手クラスのメンバーで親睦会を兼ねて、カレーを作りました!
何事も体験というこで、料理を初めてする子もいました^^
自分たちで作ったカレーは格別に美味しかったようです!
極真会館総本部道場 澤村勇太
公益財団法人 全日本空手道連盟の講師の指導による第46回目の講習会が7月1日(土)本部直轄代官山道場にて実施された。
15:00からの形(型)講習は糸東流の関根寛和先生の指導で行われ、最初にセイエンチンの部分練習から稽古が開始された。まず四股立ちの移動が行われ、先生から「セイエンチンはしっかり腰を落とした四股立ちがいかにキープできるかがポイントになります」と話があり、四股立ちから前後の下段払いの部分では「前後の動きの中で、頭の高さを変えない、体を上下させない、止まる時はピタッと止まる。前に出る時は軸だけが前に出て体は後ろに、逆に後ろに下がる時は軸だけ後ろで体は前に持っていく意識で行うと動作がしやすくなります」と解説があった。続いて四股立ちで掛け手から上げ突き、裏打ち、下段払いの動きでは「セイエンチンの形には足腰の鍛錬の意味もあり、やりにくい体勢でいかに素早く動くかがこの部分練習のテーマでもあります。そのためにも、ボディバランスを意識することが大切です」との説明があり、部分練習の後はセイエンチン全体を通した形を行った。
次に前回行った3人1組で各グループごとにオリジナルの団体形の分解を披露する稽古に移り、まずグループでセイエンチンの技を取り入れた分解を考える時間が約20分間設けられ、その後に5組に分かれた各グループごとに全員の前で発表してこの日の形講習を終えた。
16:00からの組手講習は土佐誉樹彦先生の指導で、土佐先生の道場から高校生の川又慶太朗選手が指導補佐として参加した。まず2人組で打ち込みの稽古から開始され、最初は刻み突き、次に相手の刻み突きを捌いて中段へ逆突き、続いて相手の刻み突きに対してボクシングのダッキングの要領で潜りながらかわして反撃、最後はダッキングでかわして踏み込む足を相手の後方にかけて足掛けで倒す稽古が行われた。
続いて試合形式の組手稽古が行われ、髙橋佑汰と上田幹雄、また川又選手と彼ら2人、参加者同士など様々な順で組手の手合せが行われ、土佐先生からは「相手の攻撃に対して真っ直ぐ下がらない。下がる時は腰や姿勢は低いままで相手の2打目3打目を捌いたり、円の動きで横に回って相手の攻撃を当てさせない」「試合では副審が取らなければポイントにならないので、4人の副審が認識できるように引き手をしっかり取って残心を示す」等、組手の中で気付いた点の指摘や解説があった。
また組手の中で相手の足を蹴って、即座に上段突きを入れる攻防の際には「人間の脳は2つのことを同時に認識することはできないので、足を蹴って相手の意識を下げてから上段を突く時間の間隔が短ければ短いほど相手は反応しにくくなります。ですから下を蹴った後は、瞬時に上段へ突きを伸ばし、引き手を取ってポイントを取ること」との説明があり、この日の講習会は終了した。
極真会館総本部道場 澤村勇太
公益財団法人 全日本空手道連盟の講師の指導による第45回目の講習会が6月24日(土)本部直轄代官山道場にて実施された。
15:00からの形(型)講習は糸東流の関根寛和先生の指導で、最初に先生から「団体形の分解を皆さんも見たことがあると思いますが、今日は通常の分解ではなくセイエンチンの技を使った団体形の分解を行いたいと思います。団体形の分解は大きなアクションが目を引きますが、それらは形の一部の技を用いて独自に技を組み立てたものです。今回は皆さんで技を考えながら工夫してみましょう」との話があった。
まずセイエンチンを2回行い、次に3人一組で団体形の分解の演武の稽古に移った。最初にセイエンチンで相手の突きを受けてその腕を取って技を返す攻防で、それぞれの組ごとに突きや蹴りを返したり、あるいはそのまま投げて倒したりというように創意工夫する時間が設けられ、その後に各組ごとに全員の前で披露した。
関根先生は「形は1対1ではなく、1対複数の相手を想定して作られています。団体形も3人一組であれば2人の相手にどう向かっていくのかを考えながら行うことが大事です。また、分解ではその技や攻防にいかにリアリティを持たせるのかを考えながらやること。そうすることで相手との距離や、捌き方、投げて倒すなど相手の体をコントロールすることを学び、それらは組手に応用できるものだと思います」と説明があった。
最後にセイエンチンの中の相手の蹴りと突きを連動して受けて技を返す攻防を用いた分解を行ってこの日の形講習を終えた。
16:00からの横道正明先生の組手講習は、まず前回に続いて両足にゴムの輪をつけて、左右の構えを切り替える稽古が行われ、横道先生からは「切り替える時は肩で回るのではなく、腰を切る意識で行うこと。足のゴムは構えを切り替えても歩幅を変えないという意味があります」と説明された。
続いて2人組になり、攻撃側が刻み突きや前蹴りを出し、ゴムの輪をつけた相手はその攻撃に対して構えを切り替えて受けて技を返す稽古が行われ、横道先生からは「相手の技が来る前から動くのではなく、相手の技をよく見てギリギリ当たる寸前で瞬間的に素早く構えをスイッチする。早く動くと相手に動作を読まれてしまう」と注意があった。
その後に今回行った構えの切り替えを意識した試合形式の組手、最後は白色と黄色の2つの電球で、構えを切り替えてからの突きや蹴りを繰り出す反応に重点を置いた稽古を行い、この日の講習会は終了した。
極真会館総本部道場 澤村勇太